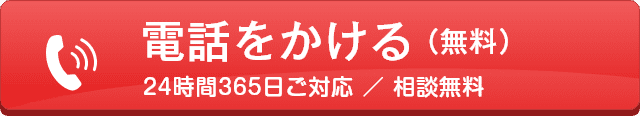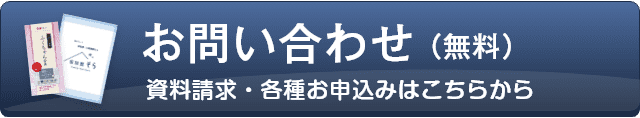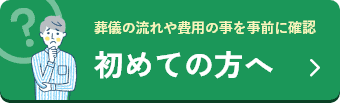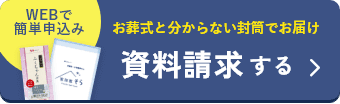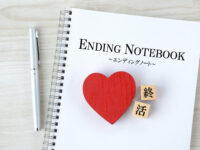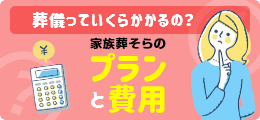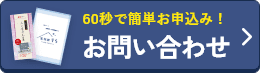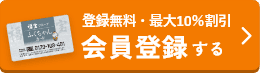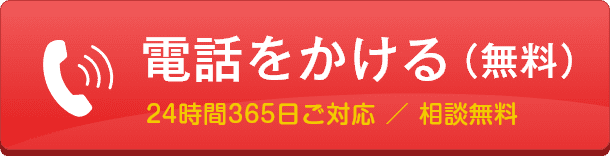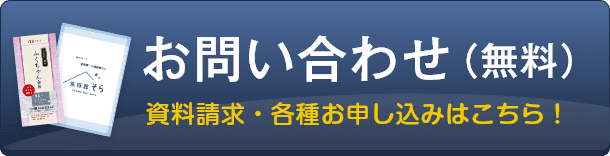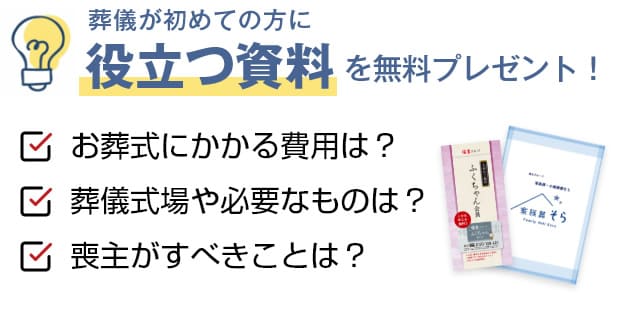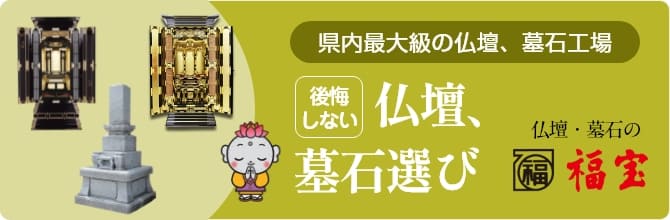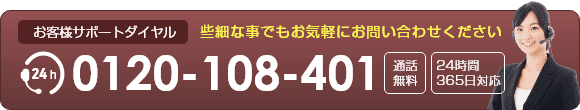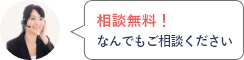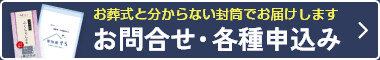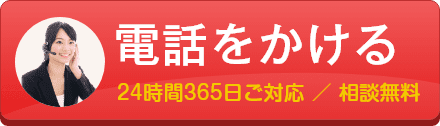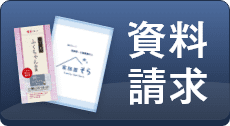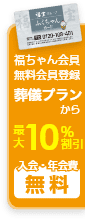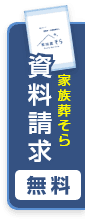近年、「終活」という考え方が広く浸透し、エンディングノート、遺言書、生前遺品整理等「自分の人生の最期を自分らしく迎えるための準備」を行う人が増えています。その一環として注目されているのが「葬儀の生前準備」です。
これまで葬儀は、亡くなった後に大きな悲しみの中、家族が慌てて手配するのが一般的でした。しかし、社会の変化や価値観の多様化、さらには少子高齢化の進行により、「自分の葬儀は自分で決めておきたい」と考える人が増えています。では、昨今の葬儀や生前準備の傾向にはどのような変化が見られるのでしょうか?今回のコラムでは、その背景や現状について詳しく考察します。
新潟市の小規模葬儀・家族葬から納骨、法要のご相談は【家族葬そら】
メニュー
はじめに
葬儀の生前準備とは
「葬儀の生前準備」とは、自分自身の死後に行われる葬儀について、あらかじめ希望する葬儀内容を自身で決めておき、その内容を家族に伝え、共有しておくこと指します。自分の人生の終わり方について考え、自分の意志で葬儀の内容を組み立てておくことで、遺された家族への負担を減らすと同時に、自分らしい最期を迎えることが可能となります。
特に近年は、高齢化社会や核家族化の影響で、家族や親族に対する負担を減らすために、また、自分の希望通りの葬儀を実現したいという思いから、葬儀の生前準備に取り掛かる人は近年増加しています。
葬儀社主催の「事前相談」との違いは?
最近、葬儀社が実施する「葬儀の事前相談」と今回のテーマである「葬儀の生前準備」は混同されがちですが、この二つには明確な違いがあります。
葬儀の事前相談
葬儀社が主催する「事前相談」は、将来の葬儀に備えて家族や本人が葬儀社に相談し、葬儀の流れや費用について情報を得ることです。事前相談はあくまで情報収集の段階であり、具体的な契約や手配は行われません。事前相談の結果、葬儀内容が決まったとしても、契約や支払いは死後に行われることが一般的です。葬儀社によっては「事前相談」に参加することで大きな割引特典を受けられるケースもあります。
家族葬そらでは、いつでも、何度でも相談可能な「事前相談会」を随時実施しています。
葬儀の生前準備
一方、葬儀の生前準備は、他の「終活」同様、心身ともに元気な期間に自身の死後に行われる葬儀について、あらかじめ希望する葬儀内容の希望を、家族に伝え、相談し共有しておくこと指します。自身に万が一の場合は、家族はその葬儀形態、規模、予算感などを元に葬儀社と相談し、希望を叶えてくれる先と契約します。人によっては葬儀費用の準備も生前に手配するケースも見受けられますが、その点も家族としっかり話し合う必要があります。思考もしっかりしている時期に自身の葬儀の生前準備を行えば、希望する葬儀の内容が概ね反映され、家族が迷うことなく準備を進めることができます。
生前準備、誰がするの?
葬儀の生前予約を行うのは、基本的にはご本人ですが、以下のようなケースも見受けられます。
自分自身のために生前準備する場合
「自分の死後、家族に負担をかけたくない」「自分らしい葬儀を実現したい」と考える人が、自ら葬儀の生前準備を行うケースが多く見られます。特に高齢者や、独身者、子供がいない人、遠方に家族がいる人などが、自分で段取りを決めておきたいと考えることが多いです。
親や配偶者のために子供が準備する場合
親が高齢や認知症などで判断能力が低下している場合、子供が親の意向を確認しながら葬儀の生前準備をするケースも数多くみられます。この場合、親の思考がしっかりしているうちに意思確認を行っておくことが大切です。
葬儀の生前整理、どんな人に向いているの?
葬儀の生前整理は、以下のような人に向いています。
家族に負担を掛けたくない人
葬儀の準備や執り行いは、精神的にも金銭的にも家族に大きな負担を強います。生前準備をすることで、家族は葬儀準備の心配から多少なりとも解放され、安心して故人を見送ることに専念出来ます。
自分の希望通りの葬儀をしたい人
「自分はこういう形で送られたい」「近しい親族と家族葬にしたい」といった明確な希望がある人には、葬儀の生前準備が最適です。自分の希望が概ね反映されることで、後悔のない最期を迎えることができます。
独身や身寄りのない人
家族や親族がいない場合、自分の死後の手続きを誰が行うか心配になることがあります。
元気なうちに自分の葬儀の生前準備をしておくことで、不安を軽くすることも可能です。
葬儀の「生前準備」、どこまで決められるの?
生前準備で決められる内容
知人や親族の葬儀に参列して「自分の葬儀はこうしたい」「もっと小規模な葬儀がしたい」など、感じたことはありませんか? 葬儀の生前準備では、以下の項目について自身で葬儀各項目の希望を家族と話し合っておくことをおすすめします。
葬儀の形式
宗教・宗派についての希望
葬儀の宗教や宗派も、生前準備でイメージしてみましょう。
仏教式:最も一般的な形式で、僧侶による読経や戒名の授与が行われます。
神道式:神職が執り行う儀式で、故人の霊を守護神として祀る形式です。
キリスト教式:神への感謝と祈りの中で故人を送る形式。
無宗教式:宗教儀式にこだわらず、自由なスタイルで行います
会場の選択
葬儀会場も自分でイメージしてましょう。以下のような選択肢があります。
自宅:昔ながらの自宅葬。家族の負担が大きいです。
葬儀社ホール:葬儀の設備が整っており、家族の負担は比較的少ない。
寺院:宗派や信仰に基づいた葬儀を希望する場合は、菩提寺での葬儀も可能ですが僧侶との相談が必要です。
祭壇・棺・遺影のデザイン
葬儀の生前準備では、葬儀の細部に至るまで自分の好みを反映させる人も増えています。
祭壇のデザイン:シンプルなものから豪華なものまで、選べるシステムとなっている葬儀社が多いようです。実際の葬儀では棺の種類:木棺、布張り棺等、材質やデザインを指定できます。最近、葬儀社が主催する事前相談のイベントなどでは、来場者が実際に棺に入ってみるコーナーもあり、体験してみるのも一興です。
遺影写真:自分自身がお気に入りの写真をあらかじめ選んでおくことで、家族も安心出来ます。遺影写真は葬儀後も長く飾ることになるので自分で決める人も多いです。
参列者の規模と招待者について家族と共有しておく
「誰に参列してほしいのか」「どの範囲まで招待するのか」を事前に家族と共有しておくことが肝要です。葬儀スタイルによっても異なりますが、親族やごく親しい友人、取引先・仕事関係者、友人関係等、参列してもらいたい招待者リストを試しに作ってみると自身の交友関係に置いて新たな発見もあります。
逆に招待しない、招待したくないリスト等、過去の関係性などを踏まえ、参列を控えてほしい人を共有してもよいでしょう。
音楽(BGM)・演出・花の種類
自分らしい葬儀を演出するために、会場で流すBGMや、思い出コーナーの設営、映像や写真スライドショーなどを事前に準備する人が増えています。人生の思い出をまとめた映像を上映することで、参列者に自分の人生の歩みを伝えることが出来ます。
祭壇を飾る花の種類・色合いも自分が好きな花で祭壇や会場を飾ることで、個性を演出できます。
香典・会葬礼状の取り扱い
生前準備では、香典や会葬礼状に関する方針も家族と話し合っておいた方が、自分らしい葬儀を叶えられます。
香典の受取について、受け取るかどうか、また受け取り辞退するか、家族と話してみましょう。
参列者への感謝の気持ちを込めた会葬礼状の内容も、近年では自身で書く人が増えています。
納骨・供養の方法
葬儀後の納骨や供養の方法についても、自身の希望をしっかりイメージして家族に伝えておきましょう。
墓地への納骨:家族の墓や新たに購入した墓地に納骨する方法。
永代供養:寺院などで永代にわたって供養してもらう方法。
樹木葬・散骨:自然に還ることを望む場合は、樹木葬や散骨を選ぶこともできます。
生前準備では不可能な事柄
葬儀の生前準備では、葬儀の形式や会場、費用など多くのことを家族と相談して希望を共有することが可能です。実際の葬儀では、すべての希望を実行することは不可能です。この項目では生前準備では不可能な事柄を検証してみましょう。
参列者について
葬儀の生前準備の際に、家族や親しい友人、仕事関係者など、参列を希望する人のリストを作成しておくことは可能です。しかし、最終的な参列者はその日にならないと分かりません。
健康状態の変化:高齢の参列予定者が葬儀当日に体調不良で来られない可能性があります。
遠方からの参列:親族や友人が遠方に住んでいる場合、日程や交通手段の都合で参列できないケースもあります。
関係性の変化:長い年月の間に交友関係が変わり、予想していた参列者が疎遠になっている可能性もあります。
家族の意向による変更
葬儀の生前準備をしていても、最終的な葬儀時は遺族が執り行うことになります。その時点の家族の意向によって内容が変更されることがあります。
・葬儀形式の変更:生前は一般葬を希望していても、家族が「近しい人だけで、こじんまりと送り出したい」と判断し、家族葬に変更する可能性があります。
・宗教・宗派の違い:無宗教葬を希望していた場合でも、遺族・親族の意向で仏教式に変更されることがあります。
・葬儀予算:本人の希望を聞いて準備していても、その死亡時点での経済状況が変化した場合、家族が費用を抑える方向で変更を求めることもあります。
葬儀の生前準備をする際は、自分の希望をエンディングノートなどに明記するだけでなく、家族とも十分に話し合って理解を得ておくことが重要です。また、家族が故人の意思を尊重できるよう、「自分が望む葬儀の理由や背景」についても伝えておくことで、意向の食い違いを防ぐことができます。
まとめ
葬儀の生前準備は、家族の負担を減らし、自分の希望通りの葬儀を実現するための有効な手段です。生前準備を検討する際は、自分や家族の状況を十分に考慮し、適切なタイミングで取り組みすることが大切です。
葬儀の生前準備は、自分の人生の終焉を、自分らしく、そして家族に負担をかけずに迎えるための有効な手段です。決して縁起が悪いものではありません。むしろ、自分の人生を最後まで主体的に生きるための、前向きな選択と言えるでしょう。
家族葬そらでは万が一の時に慌てないためにも「事前相談」を推奨しています。
●事前相談はこちら
https://familyhall-sora.jp/advance-consultation/
新潟市・近郊エリアでの家族葬は家族葬そらにお任せください
新潟市・近郊エリアに12式場を展開する家族葬そらは、はじめての葬儀でも安心して執り行える1日1組限定の貸切家族葬専用ホール(家族葬式場)です。一級葬祭ディレクター他経験豊富なスタッフが、ご遺族の心に寄り添い、故人への感謝を最大限にお伝えできるよう、無理のないプランとスムーズな葬儀の段取りで親身にサポートいたします。
また、福宝グループの葬儀社として葬儀だけでなく、仏壇・墓石・霊園などを通じて、皆様を支えて参ります。どんな小さなことでも構いません、家族葬はもちろん、葬儀に関わるお困りごとや疑問は家族葬そらへお問い合わせください。24時間通話無料でご相談に応じます。
葬祭ディレクターがご遺族様を
丁寧にサポートします
-

みやじま
-

きりゅう
-

みまた
-

さいとう
- 実際にかかるお葬式の費用や内容
- 式場の設備や雰囲気
- いざという時の準備や流れ
24時間365日対応
専門スタッフが疑問にお答えします
-

たかだ
-
お客様のご意向に沿うようにできる限りのお手伝いをさせていただきます。
様々なお別れの仕方のご希望があると思います。無宗派葬の場合はいくつかのご提案をさせていただき、暖かく心に残るお別れの場を準備いたします。
-

ほり
-
葬儀への不安を払しょくし、ご要望を叶えるべくサポートいたします。
皆さんからの希望や要望、故人の人柄を表すものや葬儀全体の進め方、記憶や形に残るものなど。出来るだけ叶えたいと思っています。