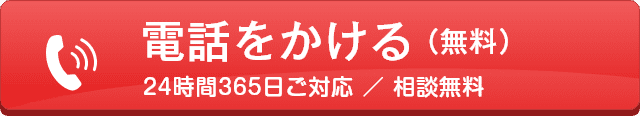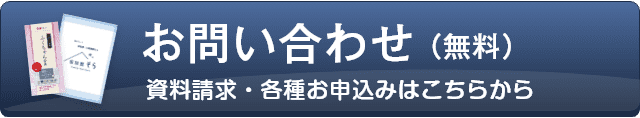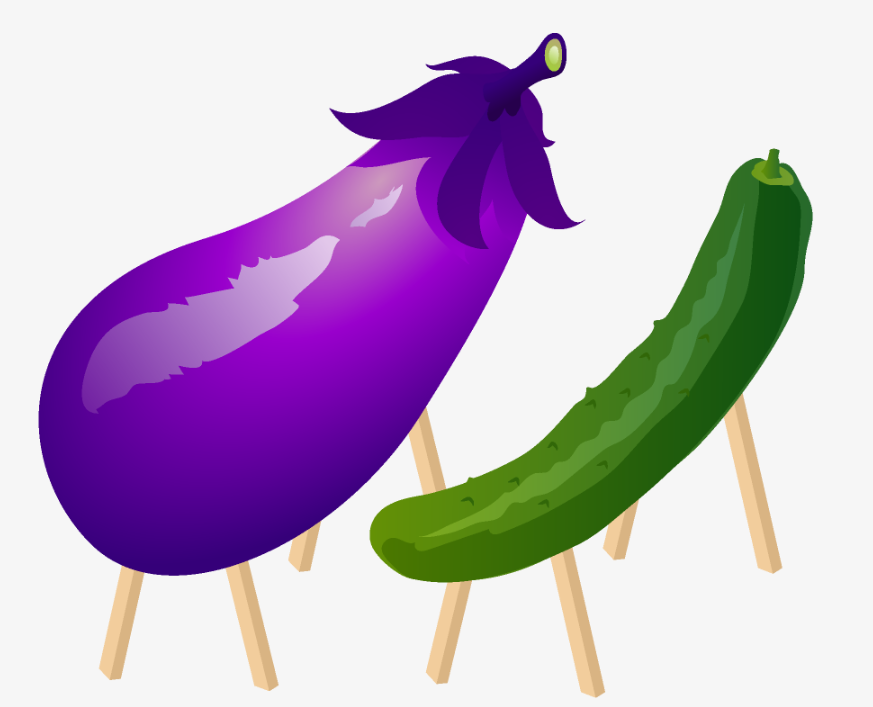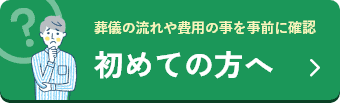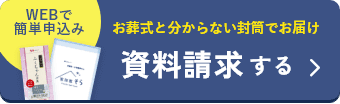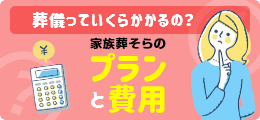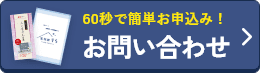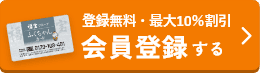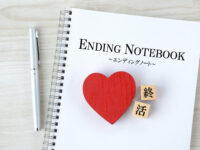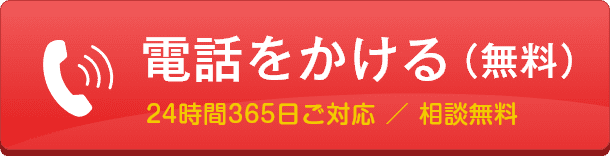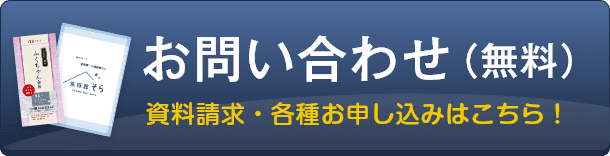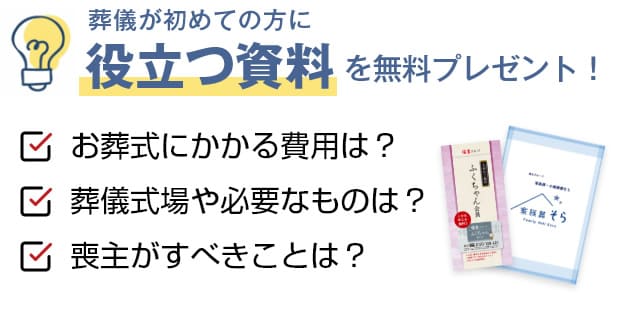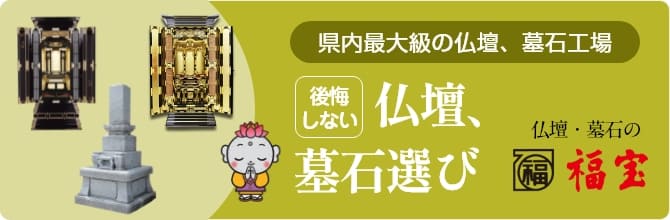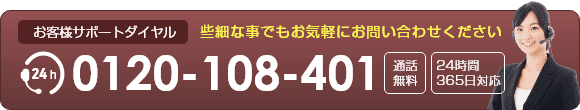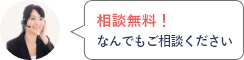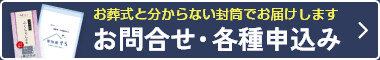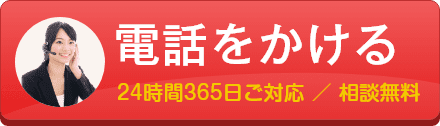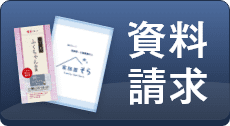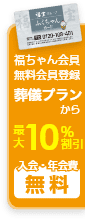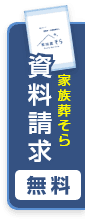はじめに
近年、故人や喪主、遺族の希望を大切にした「家族葬」を選ぶ方が増えています。身近な家族・親族や親しい友人だけで静かに「家族葬」は、故人との最後の時間をゆっくりと心ゆくまで過ごすことが出来る家族葬は、故人への思いや感謝をより深く表現できる葬送の新しいかたちといえるでしょう。しかし、参列者が限られるからこそ、葬儀後の供養や心づかいがより大切になります。特に、日本の伝統行事の中でも「お盆」は、故人を偲ぶとても大切な風習です。
新潟県下越地方や新潟市周辺をはじめとした地域では、先祖や故人の霊を迎え入れ、感謝とともに供養する風習が根付いています。「家族葬」という葬儀スタイルを選んだ場合でも、お盆の供養を「故人をしっかり送る大切な場面」として重視したいものです。本コラムでは、家族葬後のお盆の過ごし方や供養のポイント、心づかいについて詳しくご紹介します。但し「お盆はこうあるべき」と言うことはなく、あくまでも基本的な心構え、過ごし方について記述しています。ライフスタイルの多様化とともにお盆の捉え方も変化しています。あくまでも参考してお読みいただけたら幸いです。
家族葬後のお盆の意義
家族葬後のお盆は、故人への想いを改めて深める機会であり、「家族だけだからこそ丁寧に迎えたい」と考える方が増えています。現代ではライフスタイルの多様化が進み、家族の形や価値観も大きく変化しています。都市部への移住や核家族化の影響により、仏事や供養の伝統が次第に薄れつつある今だからこそ、「お盆」を通してご先祖様や故人を想い、家族が一堂に会する意義は、ますます大きなものとなっています。
地域で守られてきた風習を、今の時代に合った形で子どもや孫へ伝え、”地域の伝統”として継承していくことも大切な心づかいです。
家族葬後のお盆は、静かでありながら、家族の絆を再確認できる貴重な時間となるでしょう。大切なのは、何より「故人を偲ぶ気持ち」なのですから。
初盆(新盆)とは?特別な意味と準備
故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を「初盆(はつぼん)」または「新盆(にいぼん)」といいます。新潟県下越地方や新潟市周辺でも初盆(新盆)は特別な意味を持ち、通常より丁寧に供養することが大切にされています。
白提灯を用意し、故人の霊が迷わず帰ってこれるように飾る風習があります。家族相互の新盆(初盆)は葬儀に来られなかった親族や友人が自宅やお墓にお参りに訪れることもあります。家族葬だった場合、改めて訪問してくださる方もいるため、準備は早めに進めましょう。
仏壇のお掃除
亡くなった時は悲しみと喪失感、そして何かと気忙しい時だったので、仏壇の掃除までは気が回らない場合が多いと思います。新盆は是非とも仏壇をキレイに掃除しましょう。清掃後の仏具の配置がわからなくならないために、事前にスマートフォン等の写真機能で撮影する事をおすすめします。清掃後は画像を見ながら元の配置通りにすれば安心です。仏具用専門のクリーナー等もあるようですが、家庭用洗剤を薄めにしてしっかり絞ったキレイな布巾で丁寧にふき取りましょう。
自信の無い方や、忙しくて対応できない方向けに「家族葬そら」のグループでもある「仏壇・墓石の福宝」では仏壇清掃も仏壇職人が自宅まで行ってプロの技術でキレイに確実にしてくれます。新盆前には是非ともやっておきたいことのひとつです。
■福宝 仏壇お掃除
https://www.fukuhou.jp/butsudan-cleaning/
福宝では仏壇のお掃除含めて、今後の仏事やお墓、永大供養、霊園等の相談にものってくれます。
お盆の迎え方と具体的な流れ
近年、生活習慣の変化やセレモニーの多様化により、お盆の迎え方や具体的な流れは、それぞれの家や喪主の考えにより、大きく変わってきているのが現実です。特に新潟市内中心部では核家族化も進行し、出来るだけシンプルに過ごす家族も多くなってきています。参考までに昭和~平成まで行われており、現在も引き続き実施されているお盆のセレモニーの一部を紹介します。
お盆の期間は地域により異なりますが、新潟市内周辺の場合、一般的に8月13日から16日までの4日間です。新潟では13日に迎え火(盆提灯等)を焚いて先祖をお迎えし、16日に送り火(精霊流し等)を焚いて見送るのが一般的です。
・13日:迎え火を焚き、精霊棚を整えます
・14〜15日:家族でお参りや供養、親族との交流
・16日:送り火を焚いて見送り
家族葬であっても、この一連の流れを大切に行うことで、故人の魂をきちんとお迎えし、送る気持ちを伝えることができます。
精霊棚(しょうりょうだな)や盆飾りの整え方
精霊棚は、故人やご先祖様をお迎えするための祭壇です。地域や宗派により多少異なりますが、基本的には位牌、仏具、供物(果物や野菜、菓子など)を供え、花や提灯を飾ります。新潟市周辺では桃やトマト、きゅうり、枝豆などが一般的です。お菓子の場合は故人が好きだったモノや日持ちのするゼリーや焼き菓子が多く使われているようです。
新潟の下越地方周辺では、野菜で作った精霊馬(キュウリやナスで作る馬や牛)を供える風習があります。これには「馬で早く帰り、牛でゆっくり戻る」という意味が込められています。
家族葬後のお盆(新盆または初盆)に精霊棚を整えることで、改めて故人の存在を家族で感じ、思い出を語り合う時間が生まれます(新潟県下越エリアでは比較的多い宗派=浄土真宗では精霊棚を設ける習慣はありません)
迎え火・送り火の心づかい
迎え火は、故人やご先祖様が家に迷わず戻れるように焚く火です。調べてみると下越地方周辺では、玄関先や庭先で焙烙(ほうろく)皿にオガラ(麻の茎)を燃やす方法が一般的です。
送り火はお盆最終日に行い、帰る霊を見送るための儀式です。小さな火でも心を込めて焚くことで「また来年もお帰りください」という気持ちを伝えます。
家族葬を選んだ場合、この迎え火・送り火を家族で静かに行うことで、心を通わせる特別な時間になります。近年では安全性を優先してアウトドアライフで使用する「電気式ランタン」や自宅にある「懐中電灯」で代用するところもあるようです。正式な器具でなくても故人を偲ぶ気持ちがあれば問題ありません(新潟県下越エリアでは比較的多い宗派=浄土真宗では迎え火・送り火を焚いたりする習慣はありません)
お盆のお墓参りの作法と注意点
お盆の期間中に家族でお墓参りをすることはとても大切です。お墓を掃除し、花、お供物や線香を供え、家族で故人の冥福を祈ります。
お墓参りの際は、以下の作法を意識しましょう。
・事前に墓石や周辺をきれいに掃除する
・供物は痛む可能性があるため、持ち帰る方が望ましい。
・ご近所のお墓にも軽く手を合わせる。掃除のために決して登ったりしない。
下越地方新潟市周辺では、周囲とのつながりを重視するため、お墓参りの際に親族や近所の方々と挨拶を交わすのも大切な習慣です。
お盆期間中、故人を偲ぶ時間のつくり方
ご葬儀の際に故人に直接お別れを告げられなかった友人や知人がいる場合があります。お盆はそうした方々と共に故人を偲ぶよい機会です。
家の中で故人の写真や愛用品を飾り、思い出話をしたり、好きだった食べ物を供えたりするなど、自由な形で偲ぶ時間をつくりましょう。
子どもや若い世代にとっても、故人を思う文化を学ぶ貴重な機会になります。
親族・ご近所とのコミュニケーション
家族葬の場合、広く知らせずに葬儀を済ませることが多いため、後日「お参りに行きたい、お線香をあげさせてほしい」と申し出る親族や近所の方がいらっしゃいます。
お盆はそうした方々をお迎えするのに相応しい時期です。お盆期間中、自宅客間・仏間には簡単なお茶菓子を用意してお迎えし、故人生前の感謝の言葉を伝えすることで疎遠になっていた親族や日頃お世話になっている近所の方々とのコミュニケーションをはかる良い機会です。
こうしたコミュニケーションは地域の慣習を大切にしながら、故人の思いを共有することが、心を和ませ、信頼関係を深めることにつながります。
お盆における供養の形と贈り物
お盆には、供物や御供(おそなえ)を持参する文化があります。新潟市内周辺では、菓子折りや果物などを贈る習慣が根強いです。
家族葬の時は、香典や供物を辞退している場合でも、お盆には供養の気持ちとしてお菓子などを持って来られる方がいます。その際は無理に遠慮・辞退せずに、丁重に受け取り、後日礼状を出すとよいでしょう。
家族葬とお盆を通して伝える感謝の心
お盆は単なる故人や先祖に対しての供養の行事ではなく、つながりを再確認し、感謝の気持ちを伝える大切な期間です。
家族葬を選んだからこそ、周囲とのつながりや故人の思い出をより丁寧に大切にすることができます。
地域の風習に従いながらも、心からの供養を行うことで、家族も故人も安らぎを感じられるでしょう。
お盆の供養を通して、家族の絆が深まり、これからも故人が見守ってくれていると感じられるような時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
日本古来のセレモニーが多様化した現代に置いて、比較的自由度の高い葬儀=「家族葬」の後、どのようにお盆を迎えるかは、家族によってさまざまです。しかし、共通するのは「故人を偲ぶ心と気持ち」です。
特に初盆は、とても重要な供養の場です。
地域の風習を尊重しながら、自分たちのペースで入念に準備し、心を込めて故人をお迎えください。
「家族葬そら」では、新潟県内の皆さまに寄り添った葬儀サービスを提供するだけでなく、ご葬儀後の法要や墓石等の相談をお受けしております。ひとりで悩まず、仏壇・墓石の福宝グループの「家族葬そら」主催の「無料相談会」でお気軽にご相談ください。
家族葬そらでは万が一の時に慌てないためにも「事前相談」を推奨しています。
●事前相談はこちら
https://familyhall-sora.jp/advance-consultation/